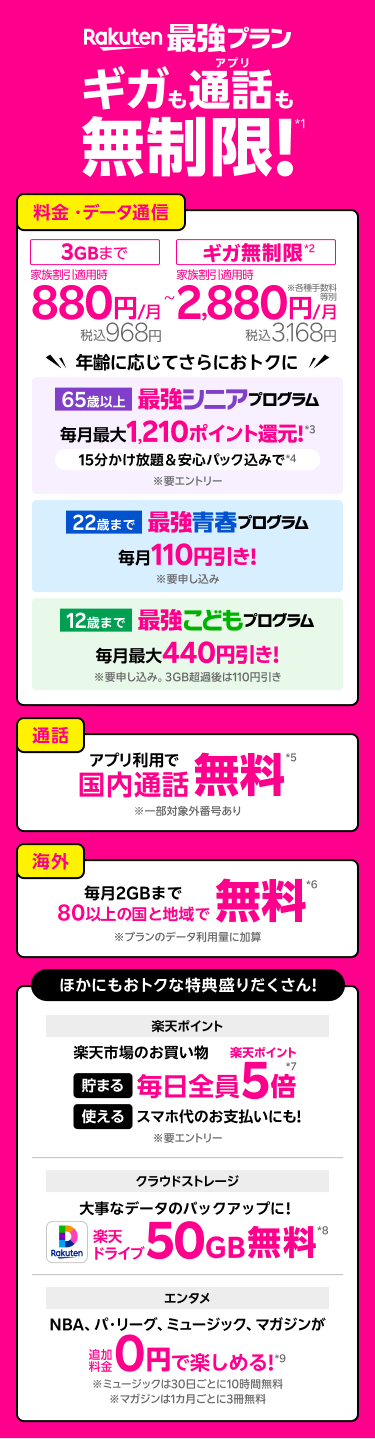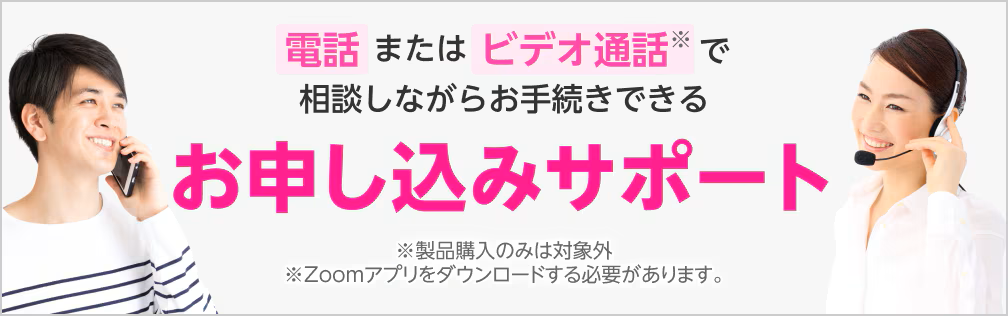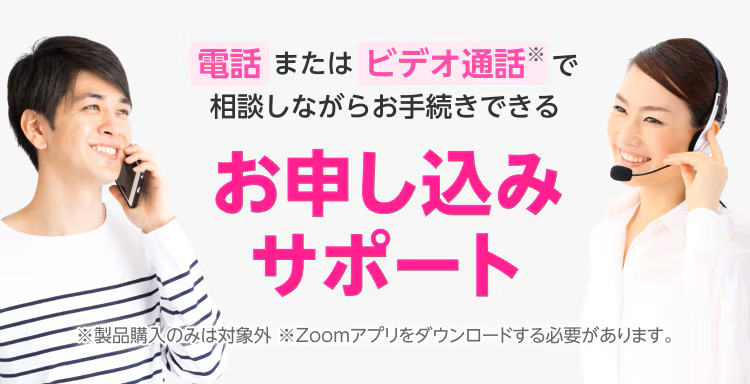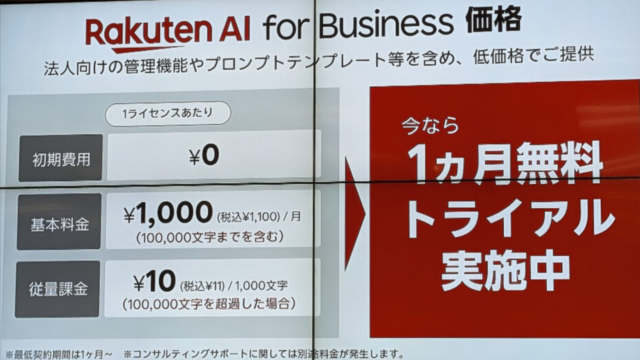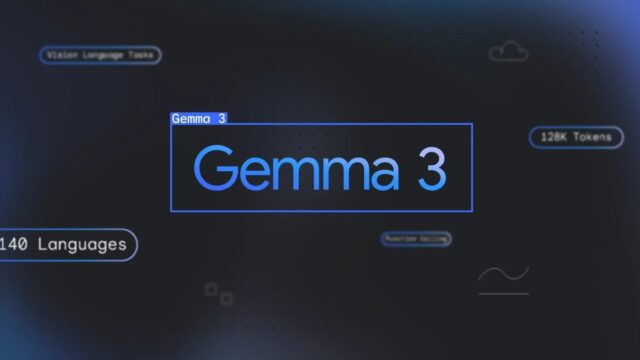AIエージェントを新たな「人材」として迎えるための指針

AIエージェントを自社の新しい「人材」、つまりチームの一員として迎え入れる ―― そんな光景が現実のものとなりつつあります。
AIの技術が成熟するのに伴い、「デジタル労働者」と呼ばれるAIエージェントの供給が爆発的に増加し、優秀なワークフォース(労働力)の定義自体を変えつつあります。
これまで人間の独壇場と考えられていた分野にもAIが参入し、かつて自動化は無理だと言われた多くのタスクをこなしています。
その結果、セールスフォースのマーク・ベニオフCEOは、デジタル労働者による市場規模が近い将来数兆ドルに達する可能性があるとの見方を示しています。
こうした状況を踏まえ、企業は将来の展望を大きく見直す必要があります。
ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)とデジタル・データ・デザイン研究所の最新の研究によれば、AIエージェントはもはや単なるアシスタントではなく、「デジタル・チームメート」とも言える新しいカテゴリーの人材になりつつあるのです。
この新しい仲間を最大限に活用するために、人事部や調達部門のリーダーは、デジタル労働者を組み込んだハイブリッドチームを構築するワークフォース戦略や人材戦略の策定に着手する必要があります。
いち早くこうした準備に時間をかけた組織は、単に業務効率が向上するだけでなく、よりスケーラブル(拡張可能)でレジリエント(回復力の高い)な協働体制を築くことができるでしょう。
この変化はすでに現実になり始めています。
例えば、大手コンサルティング会社のデロイト トーマツ コンサルティングは、あらゆる法人向けサービスにAIエージェントを活用していく方針だと報告しています。
その一環として、顧客企業の業務最適化に向けて多くのタスクをまとめて担う「マーケティング・エージェント」といったAIの導入も進められています。
また、人材サービス世界大手アデコから独立した企業であるr.Potential(アールポテンシャル)は、人間だけでなくAIも含めた労働力を企業に提供するビジネスモデルに転換し、自社モデルを見直し始めています。
新しい環境で成功するには、AIを自社のワークフォース戦略に積極的に統合していくことが欠かせません。
今すぐ行動を起こした人事や調達部門のリーダーであれば、AIをどのように選定・調達し、社内に組み込み、ガバナンス(規制)していくかを自ら主導できます。
しかし対応を躊躇しているようでは、新たな成長機会を逃すおそれがあります。
さらに悪い場合には、コンプライアンス上の問題や倫理的な問題、業績への悪影響など、予期せぬトラブルに直面する可能性すらあるでしょう。
これは破壊的テクノロジーに直面した際の企業戦略全般に共通する懸念事項です。
もはや「新しいテクノロジー(とりわけAI)はいつの間にか消えてくれるだろう」と期待して見て見ぬふりをすることはできません。
世界の様相が変わりゆく中、変化に適応する方法を深く理解するためにも、リーダー自らが自社システムの構築に深く関与していく必要があるのです。
対応が遅い企業は、この先トップクラスの人材を確保することにも苦労するでしょう。
求職者側でも、AIによってサポートされたスマートなワークフローを通じて自分の生産性や創造性を高めたい、という期待が高まっているからです。
一方、俊敏に動く競合他社はAIを事業モデルに直接組み込み、追加の人員を増やさなくてもアウトプットを飛躍的に拡大し、学習による改善サイクルも加速させています。
さらに、大企業や政府といった顧客側が強力かつ監査可能なAIポリシーやガバナンス体制をパートナー企業に求め始めれば、この分野で未成熟な組織は不利となり、重要な入札案件や提携の機会から外されてしまう危険性もあります。
つまり、何もしないことは単にチャンスを逃すだけでなく、極めて現実的なビジネスリスクを招くのです。
\楽天アカウントでログイン!/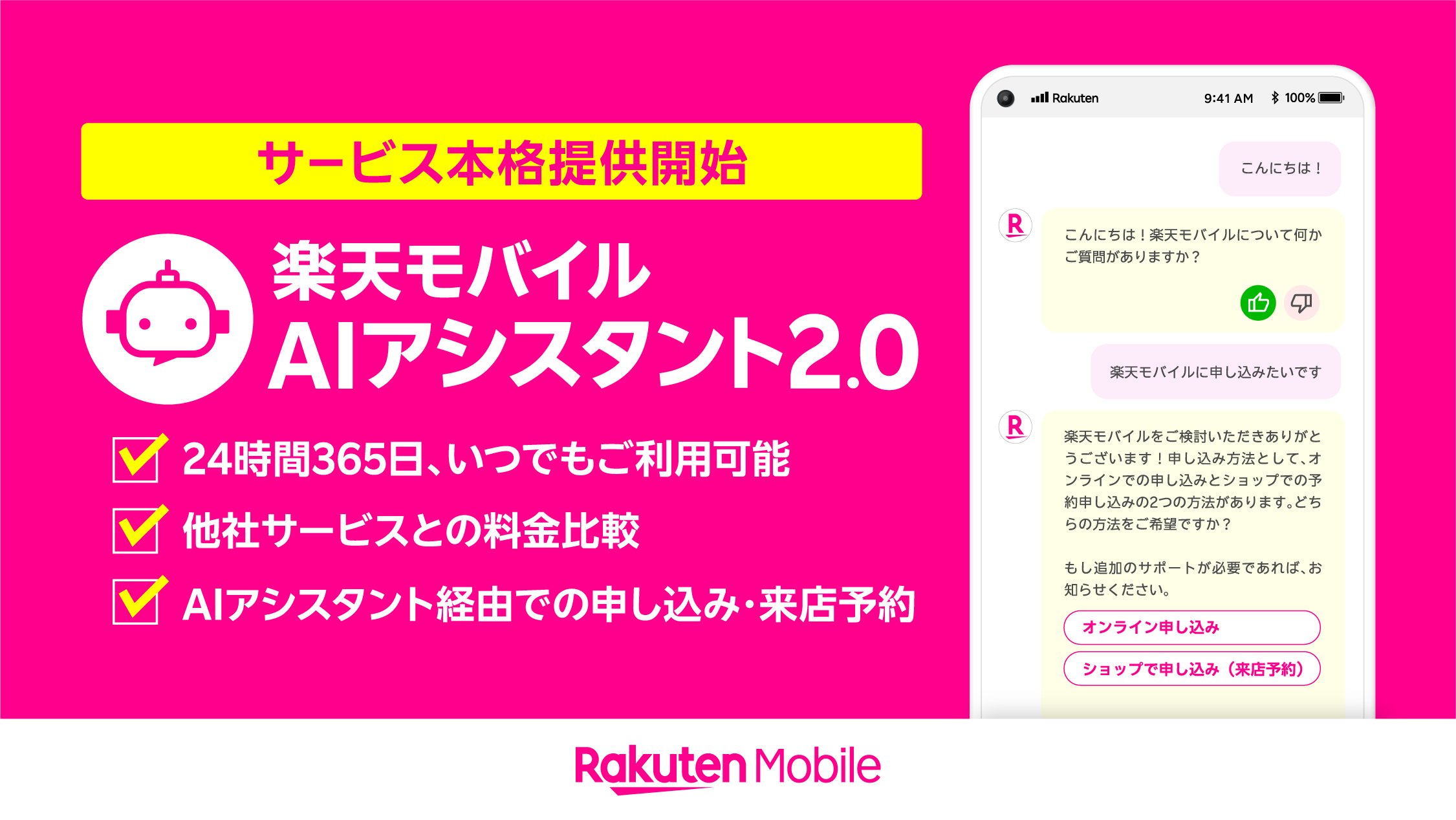
AIを効果的に活用する7つの重要アクション
上述のような背景を踏まえ、ここからは人間とAIエージェントからなるチームを前提に、新しいタイプのワークフォース戦略を設計・試行し、スケールさせるための7つの具体的アクションをご紹介します。
これらは筆者ら(HBSやオープンタレント領域の専門家)の経験に基づき、すぐに着手できる枠組みとしてまとめたものです。
自社で実践する際の手引きとして役立ててください。
1. タスクと結果をマッピングする
まず各ポジションやプロジェクトを構成するタスクや期待される成果を細かく分解することから始めましょう。
これはちょうど、人間の候補者のコンピテンシー(能力要件)を定義する作業に似ています。
そして、どのタスクであればAIエージェントの方がよりうまく、より迅速に、しかも費用対効果高く処理できるかを特定する必要があります。
例えば、大量のデータ検証や繰り返しの多いコールセンター業務などは、AIエージェントに任せるタスクの有力な候補になります。
一方、複雑な判断や説得、深い専門知識を要するタスクは、引き続き人間の洞察が求められるか、あるいはAIを補助的に活用するハイブリッドな対処が適しているかもしれません。
ポイントは、もはや単に「労働力(作業時間)を買う」のではなく、人間とAIの組み合わせが生み出す成果(アウトプット)を手に入れるという発想に切り替えることです。
したがって、調達に関する議論を始める際には、まずタスクを徹底的に洗い出し、適切に人間とAIを組み合わせることが重要になります。
2. AIの能力を評価する
自社の特定のタスクやワークフローに対してどのAIモデルやプラットフォームが最適なのかを見極めることも不可欠です。
そのために、データ検証やコールセンターといった明らかなケースだけでなく、マーケティングアナリスト、カスタマーサポート担当、スケジューリングコーディネーターなど、社内の様々なポジションで共通する役割に対応できるAIの機能を分類し、カタログ化してみましょう。
例えば、マーケティングのコピーライティングには大規模言語モデル(LLM)が適しているかもしれませんが、製造業の品質チェックには専門特化したコンピュータビジョン(CV)系のエージェントの方が向いている可能性があります。
このように社内のAI能力カタログを作成しておけば、「とりあえず一律にAIを導入する」といった画一的なアプローチを避けられるでしょう。
調達の観点で言えば、これはAIソリューションに関する社内RFP(提案依頼書)を用意するようなものです。
どのモデルがどの課題を解決できるのかを把握し、その分野に強みと実績を持つ人材紹介会社やテクノロジーベンダーと積極的に提携しましょう。
そうすれば、実際のビジネスニーズに合わないAIモデルに法外なコストを払うような事態も防げます。
3. ハイブリッドチームを統合する
AIエージェントと人間が混在するチームを円滑に機能させるには、それぞれの役割と責任範囲を明確に線引きする必要があります。
具体的には、どのタスクをAIが担当し、どのタスクを人間が担当するのか、さらに問題が起きたときにどのようにエスカレーション(段階的な引き継ぎ)するのかを定義したハイブリッド・ワークフォース戦略を策定しましょう。
例えば、AIのチャットボットが一次対応するカスタマーサービスでは、請求金額が一定額を超える複雑なクレームは自動的に人間の担当者へエスカレートする、といったルールを設定できます。
あらかじめ役割分担やプロトコル上の「引き継ぎポイント」を文書化しておけば、組織全体で安心感と信頼を醸成できるだけでなく、役割の衝突や対応の重複も防ぐことができます。
4. ビジネスモデルとワークフォースモデルを再設計する
正社員・臨時雇用者・フリーランサー・AIといった多様な人材をどう調達し配置するか、新たな方法を模索することも求められます。
具体的には次のようなマルチレイヤーモデルの活用を検討しましょう.
- クライアント(自社)が所有するデジタル労働者
- リース型のデジタル労働者
- AI部門の完全アウトソーシング
自社の財務・コンプライアンス上の条件や戦略的ニーズに照らして、上記のモデルを最適に組み合わせてみてください。
例えば、季節的に事務処理が急増する時期にはAIエージェントを短期間リースするのが効率的かもしれませんし、逆に日常的に発生する反復的だが重要な業務は、思い切ってAI主体の外部サービスに完全アウトソーシングした方がよい場合もあります。
リーダーの使命は、このように多様なタイプの労働力を統合してマネジメントすることです。
その際、デジタル労働者特有の経済性を考慮に入れ、それに見合った新しいKPIやコスト構造を設定する必要がある点も押さえておきましょう。
5. 法的および倫理的な基本ルールを定める
AIに業務を任せるうえで、バイアスや法的責任、データガバナンス、さらには社会に与える影響に事前に対処しておくことも重要です。
そのため、法務・コンプライアンス・倫理担当のチームと協力し、AI利用に関する社内ポリシーを整備する必要があります。
このポリシーでは、AIが社内の独自データから学習する場合の扱いや学習方法、バイアスをどう検出・是正するか、個人情報や機密情報をどう保護するか、といった点を明確に定めておくべきです。
グローバル企業であれば、国ごとに異なる規制に直面することも覚悟しなければなりません。
それだけこの取り組みは重要です。
倫理面での失敗は企業の評判を傷つけるだけでなく、法規制にも抵触する恐れがあります。
現に世界各国でAI関連の法律整備が急ピッチで進んでいます。
だからこそ、法律が施行されるのを待って慌てて対応策を講じるのではなく、先手を打って社内ルールの枠組みを構築し、組織としてのAIリテラシーや倫理観を育てておくことが肝心です。
6. 技術の進化に合わせて価値を最大化し続ける
AIを導入したら終わり、ではありません。
運用フェーズでは常にパフォーマンスをモニタリングし、結果を測定し、人間とAIの最適な組み合わせを追求して改善し続ける必要があります。
単発のAI導入で満足するのではなく、フィードバックに基づいてパフォーマンスを測定し、AIのトレーニングデータを更新し、調達戦略自体も見直す ―― そんな継続的な改善サイクルを確立しましょう。
例えば、AIによるスケジュール調整ツールを導入したものの、人間の介入が頻繁に必要になるケースが多いと分かった場合、さらに高度な追加トレーニングが必要かもしれませんし、あるいは人間によるモニタリング体制を強化すべき信号かもしれません。
いずれにせよ、「一度ルールを決めたら後は放置でよい」という従来型の人事管理アプローチは通用しません。
7. 人間中心であることを維持する
AIは人間に代わって単調なタスクを処理してくれるため、人間が担う価値の高い仕事の重要性が一段と増していきます。
従業員がそうした高度な業務に引き続き取り組めるようにすれば、モチベーションを維持できるだけでなく、他社には真似できない付加価値を生み出すこともできるでしょう。
したがって、従業員がAIと協働することに慣れるための研修だけでなく、AIを活用して自分たちの仕事のインパクトを高めるための研修やスキル開発にも投資しましょう。
未来を左右する大変革に備える
AI「労働者」を直接採用するにせよ、人材紹介会社やオープンタレントのサービスを通じて調達するにせよ、次のような重要な問いを自社に投げかけてみてください.
- 自社の独自データでAIエージェントをトレーニングした場合、その結果生まれる能力の所有権は誰に帰属するのか?
- AIエージェントに「雇用契約」は必要か? 仮にAIがミスをした場合、誰がその責任を負うのか?
- AIの監督方法や公平性の確保について、未解決の課題はないか?
- ある仕事を人間とAIのどちらに任せるか、現時点でガイドラインはあるか?
- 将来的にAIエージェントがチームに溶け込み、法的または倫理的な地位すら得た場合、「仕事」の定義はどう進化しうるか?
これらの問いすべてに最初から完璧な答えを用意しておく必要はありません。
進めていく過程で指針として折に触れ自問し、少しずつ答えを見出していけばよいのです。
いずれも絵空事の理論ではなく、現実の戦略課題です。
そして、これらの難問に真っ先に向き合い解決策を講じる組織こそが、「仕事の未来」がどう姿を変えていくのか、そしてその価値を誰が握るのか ―― その主導権を握ることになるでしょう。
最後に、今後の方向性を検討する際には人間中心主義という軸足を常に忘れないでください。
確かにAIは人間よりも多くのタスクをより速く処理できますが、どんな企業であれ、最終的には人間にしか提供できない洞察や共感、信頼関係に支えられているものです。
AIの効率性を存分に引き出すことと、人間の創造性や共感力を守り高めること ―― この二つのフォーカスを両立できれば、持続可能な成長を推進する可能性を最大限に引き出すことができるはずです。
※ 本キャンペーンは、こちらの案内だけの限定優遇※ 再契約または2️⃣回線目以降もポイント獲得対象※ 終了日未定により、予告なく突如終了となる可能性あり
お申し込みサポート
お申し込みに関する疑問や不安を、オペレーターが丁寧にお答えいたします。ショップでのお申し込みと同様に、オペレーターからの質問に口頭でお答えいただきながら、お申し込みいただけます。ご相談からご契約まで、お気軽にご利用ください。
\こんな方は/
まずは下記の「ご相談窓口」へお電話ください
- 簡単な相談だけしたい
- 料金プランやオプションサービスについてまずは少し知りたい
- 現在よりも毎月の携帯電話料金が安くなるのか確認したい
- 申し込みに関する疑問を解消したい
■ご相談窓口
TEL: 050-5434-8549
営業時間:10:00~19:00(土日祝も含む)
※ スムーズにやりとりするためにも、お電話をする前に こちら からキャンペーン にご参加ください。
※混雑時はお電話がつながりにくい場合があります。
※通話料金はお客様負担となります。ご希望の場合、オペレーターからおかけ直しします。