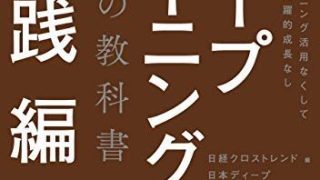飲食店DXの『ブルースターバーガー』がなぜ閉店?

焼肉のファストフード「焼肉ライク」で、コロナ禍を吹き飛ばす快進撃を続けるダイニングイノベーション。同社が低価格・高品質のハンバーガーに挑んだ「ブルースターバーガー」が2022年7月31日に全店閉店した。
創業者の西山知義氏は、「牛角」創業者でもある。現在はコロワイド傘下に入っているレインズインターナショナルで、牛角の他にも「土間土間」「しゃぶしゃぶ 温野菜」などのヒット業態を手掛けてきた。それら幾つものヒット業態の仕掛け人、西山氏が外食人生の集大成として提案したのがブルースターバーガーであり、FC(フランチャイズ)に最適な業態としていた。
ブルースターバーガーは、ITを駆使した「超スマートモデル」が特徴。オーダー・決済・受け取りまで、全てを完全非接触で実現する、ニューノーマル時代にフィットしたテークアウト専門のプチグルメバーガーを標榜。外食DX(デジタルトランスフォーメーション)の成功例と評判だった。



しかし、実際には、オープンした頃は顧客が殺到。タッチパネルの前に行列ができて、注文した後も1~2時間は優に待たされていた。決済をキャッシュレスに全振りしたのも、現金決済が主流の日本ではハードルが高かった。Gourmet113 渋谷宇田川店では、最終的に現金払い専門のタッチパネルを店頭に設置していた。
テークアウト専門をうたった創業店の中目黒店も、当初は店内に立ち食いができるスペースを確保していただけだったが、最終的にはゆっくりくつろげるように座席を設けた。「完全キャッシュレス化」「テークアウト専門店」という、2つの前提が崩れると、家賃・内装投資・人件費といった経費を極限まで軽減して商品原価に投資するモデルが、成立しなくなってしまう。
専門家の間では、「IT化とDXはよく混同されるが、ブルースターバーガーが行ったことはDXではなかった」と述べる人も多い。
IT化とは、ITを使って組織の生産性を向上させること。一方で、DXはITを手段の1つとして、ビジネスモデル等を変革して競争上の優位を確立すること。ブルースターバーガーは、接客をITに置き換えて、料理に全振りの業態を構築したが、「IT化+α」の道半ばの状態。DXに到達する以前に、原材料の高騰などの想定外の外的環境変化の影響で、撤退を余儀なくされたと推察する。

アプリ面
業務オペレーション
このようにITを活用しながらも、顧客と従業員の満足度を上げる発想にまで至らず、業務効率化の域に止まったのが、ブルースターバーガーがじり貧に終わった原因だと指摘した。
フードテックはかなり進化しているが、うまく使わなければ投資に見合ったリターンは生み出せないことは確かである。上記の意見の多くが膨大なコストが発生し、実現可能性が高いとは言えない。それくらいDXは難しいということである。IT化による可能性を示した点で、今回の「ブルースターバーガー」の施策には大変意義があった。今回の挑戦で得た経験やノウハウを活かして、近い将来再起することを期待したい。